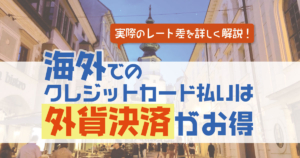「アメリカ人は気前がいい?」って本当にそうなの?と、私も初めてアメリカに行くまでは半信半疑でした。
でも実際に暮らしてみたり、旅をしたり、現地の人と触れ合ったりしていると、チップ文化や寄付のあり方を目の当たりにして、「あ、本当に気前がいい人、めちゃくちゃ多いな…」って感じることが多々あります。
アメリカにいて、接客以外の場面でもチップをもらった話
私がアメリカで驚いたのは、レストランやタクシーなどの「サービス業」でない場面でもチップをもらったことがある、という経験です。
アメリカの空港での出来事
空港のラウンジみたいなところで、スマホの充電をしていたんです。そこに通りかかった人が「ACアダプタ貸してもらえない?」って声をかけてきました。私のアダプタはポートが2つあったし、ケーブルはその人が持っていたものだから、私には別に何の負担もない状況。もちろん「いいよ、どうぞ!」と貸したら、充電後に「Thank you!」と言って、ポンと5ドル札を置いていってくれたんです。
「え、そんなに? ただポート貸しただけなのに…」ってびっくりしました。日本人的感覚だと「そんなんでお礼はいらないよ!」って思っちゃうんですが、それが相手にとってはごく当たり前の表現だったんだなと。「好意や助けてくれたことには、感謝の気持ちを形にして伝える」みたいな感覚なんでしょうか。
カフェで席を譲った話
これは別のシチュエーションなんですが、カフェに大人数のグループが入ってきたとき、私は一人で座っていたので「どうぞ、まとまって座ってください」って感じで席を自主的に移動しました。そしたらサクッと2ドルくれちゃうんですよ。「いやいや、そんな気を遣わなくていいよ」って思いながらも、相手は「ありがとう!」という気持ちを素直に形で表している感じでした。
こういう場面を何度か経験すると、「ああ、これがいわゆるチップ文化ってやつなんだなあ」と改めて実感させられます。日本だと「そこまでしなくても大丈夫ですよー」ってやりとりになることが多いけど、アメリカでは「ありがとうの気持ち+ちょっとしたお金」がセットになってる感じですよね。
プラハからドレスデンの電車でもらったチップ
これはアメリカではなくヨーロッパの話ですが、プラハからドレスデンに向かう電車の中でお年寄りの荷物を上の棚に乗せたり降ろしたり手伝っただけで、1ユーロくれました。もちろん、私は困ってそうだったから「助けるのは当たり前」ぐらいの気持ちだったんですけど、「はいこれ、ありがとう!」ってサッと小銭を渡されて。「えっ?」って一瞬戸惑いましたが、きっとその方も「自分が楽になることをしてもらったから、せめて何かお礼を…」くらいの感覚だったのかなと思います。
日本人的な感覚だと「善意は無料」みたいなところがありますよね。だから、お金をもらうとなんだか申し訳ないというか、ちょっと気恥ずかしいというか。でもアメリカやヨーロッパの文化には「手間や労力がかかったら、それに対してお礼を渡すのは当たり前」という意識があるのでしょう。そういうところがチップ文化とも繋がっているのかなと思います。
寄付も投資も多い! お金を回すアメリカ人
アメリカでは、オンライン募金やクラウドファンディングなどで寄付があっという間に高額集まったりしますよね。あと、投資にも積極的なイメージが強いです。私もアメリカにいたとき、現地の友人が普通に株や仮想通貨の話をしていたり、大学のための奨学金基金が地元の裕福な人たちからどんどん集められたりする光景を目にしました。
日本はどうしても「投資は危ない」とか「寄付はハードル高い」という意識が残ってる感じがしますが、アメリカでは「お金を回す」ことのハードルが低い。おそらく、チップ文化が体に染みついている部分も影響していて、「困ってる人にはお金でサポートする」「何かしてもらったらお金を払う(チップ含む)」という意識が強いんじゃないかなと感じます。
ストリートパフォーマーへのチップの多さ
欧米ではストリートパフォーマーって本当に多いですよね。すごい演奏やパフォーマンスしてる人が街の至る所にいる。そんなパフォーマーに対して、通りすがりにポンと1ドル入れていく人のなんと多いことか!
アメリカだと、ちょっと気に入ったら1ドル、5ドル、あるいは大盤振る舞いで10ドル、100ドル入れていく人も珍しくありません。もっとゴージャスな演奏をしているバーなんかだと、大きな額の紙幣がバンバン投げ込まれていて、「うわぁ、お金持ちの人のチップって桁が違う…」と感心したりします。
日本だと「金持ちほどケチ」なんて言われることもありますが、現地では逆に「お金のある人はチップもガツンと払う」みたいなイメージを持つことが多かったです。
一方で…「友達だからタダでやって」な日本
日本では「友達だから無料でやってよ」とか「知り合いだからただでお願い」といった話、わりとよく耳にしますよね。絵が描ける人やプログラミングできる人、デザインが得意な人に「あれやって」「これ作って」みたいなことを当然のように持ちかけるパターン。しかも「材料費かからないでしょ?」なんて言い出す人もいて、「いやいや、私の時間がかかってるんだけど?」ってモヤモヤしたり。
もちろん、仲のいい友達同士ならお金とかじゃなくて「お互い様」みたいな形で助け合うのは素敵なこと。でも、その境界があいまいになって、「無料でお願いしてもいいでしょ?」と当たり前のように思われちゃうのは困りものですよね。
アメリカだと、ちょっとしたスマホの設定を代わりにしてあげるだけでも「これ、ありがとう」ってチップやお礼があったりすることもあるみたいで、そういうところは「すごくいいなぁ」と感じます。もちろん全員がそうではないでしょうし、親しい間柄なら日本と同じく「いやいや、こんなの無料でいいよー」ってやりとりもあるでしょう。でも、「お礼をちゃんとしたい」って姿勢が浸透してるのは、やっぱりチップ文化の影響なのかなって思います。
「お客様は神様」じゃない! アメリカや海外の接客事情
「お客様は神様です」って日本ではよく言われますよね。これが良い方向に働くこともあるけど、客側が勘違いして「自分は神様」みたいな態度をとってしまうこともあって…。店員さんに対して高圧的になったり、無理難題を押しつけたりする人も実際にいます。
けど海外、とくにアメリカなんかだと、お客と店員はあくまでも対等な立場。店員さんから「Hi, how are you doing?」って挨拶されたら、ちゃんと「Hi! Good, and you?」って返すのが当たり前です。もし知らんぷりしたり無愛想な態度をとったりしたら、一気に「なんだこの人…」って嫌な顔されちゃう。
料金やチップを払うから偉いわけじゃない
料理の代金はそのまま料理に対しての対価であって、チップはサービスに対するもの。それも「立場を上にするためのお金」ではなく、「ありがとう」の気持ちを具体的に伝えるためのお金ですよね。だから、「チップたくさんあげてるんだからもっと従えよ」といった態度をとる人は、逆に周りから浮いてしまうと思います。
互いに「ありがとう」が飛び交うサービス
私が好きなのは、海外のレストランなどでお会計するときに、店員さんから「Thank you!」と言われ、自分も「Thank you!」と返すあの光景。お互いがお互いに感謝してるのが当たり前で、「もうちょっと日本でもこういうふうに対等にやりとりできたらなぁ」と思います。
もちろん、日本のおもてなし文化も素晴らしいし、サービスレベルは世界トップクラスだと思うんですが、その分、客側に勘違いを生む可能性も否めないですよね。
チップ文化が子どもの金銭教育にも影響する?意外なメリット
アメリカで暮らしていると小さい頃から「人に何かをしてもらったら、その対価を払う」という考え方が自然と身につくようです。両親が外食のたびにチップを置く姿を見て育つと、「サービスを受ける=それに応じた金額を払うのは当たり前」という意識が染みつくんでしょうね。
これって実は金銭感覚の教育にも大きく関わっていて、単にチップを「払う・もらう」だけじゃなく、「価値あるものに対してお金を払うのは当然」という考えが根づくことで、将来的に投資や寄付へのハードルが低くなる傾向があると感じます。
日本では、勉強や部活動などの成果に対して「お小遣いを増やしてあげる」といった報酬的なシステムを導入する家庭もありますが、アメリカのチップ文化はそれよりももっと日常的でリアル。レストランでもタクシーでも「あなたのサービスは○○ドルの価値がある」とか、逆に「サービスが良くなかったらチップを減らす」という行為を目の当たりにするので、良い意味で「金額=評価」の関係がダイレクトにわかりやすいんですよね。子どもにとっては、一連のやりとりを間近で見ることで「お金って単なる紙切れじゃなく、人の行動やサービスを評価する手段にもなるんだな」と学ぶきっかけになるんだと思います。
さらに、チップが高いと嬉しい、低いとちょっと残念…というストレートなフィードバックは、サービスする側のモチベーションにもダイレクトに反映されがち。こういう仕組みを幼少期から体感していると、人に対して丁寧に接することや何かしらの形で貢献する姿勢が自然に育まれやすいのかな、なんて思います。もちろん日本には日本の良さがありますが、「子どものころからお金の動きやサービスの価値を理解する」という意味では、チップ文化は思わぬところで子どもの金銭教育やコミュニケーション教育に一役買っているのかもしれません。
チップは面倒だけど、ある意味素敵
正直、アメリカで生活するならチップ文化は面倒です。レストラン行くたびに「何%置けばいいんだろう?」とか、タクシー乗ったときに「チップいくらが適正?」とか考えちゃう。慣れないと計算も間違えたり、そもそも現金が手元にない! みたいになったり…。
でも、それでもなおチップ文化を「素敵だな」と思うのは、やっぱり「感謝の気持ちを直接・形にして表す」ことができるから。口だけの「ありがとう」だけでももちろん嬉しいんだけど、そこに少しでもお金が添えられると「ちゃんと自分の行動を評価してくれてるんだな」って実感しやすいし、受け取る側も素直に「ありがとう!」ってなる。
私自身、日本ではまだまだチップ文化に馴染みがないので、「わざわざお金を渡すほどのことじゃ…」って思ってしまいがちなんですが、アメリカの気前の良さを見ていると、「困ってる人にサッとお金でサポートできるって、なんか気持ちいいな」って感じるようになりました。
いつか日本でも、チップとまではいかなくても、「誰かに何かしてもらったら、ちょっとした気持ちを渡す」という習慣がもうちょっと一般的になれば、世の中がもう少しだけ優しくなるかもしれませんね。もちろん、日本の「気遣い」や「サービス精神」はそれはそれですごく素晴らしいと思うけど、そこに少しだけ「形のある感謝」も加われば、関係がさらに豊かになるんじゃないかな…なんて思ったりします。
そういうわけで、アメリカや欧米を旅して感じる「チップ文化」や「気前の良さ」は、正直面倒なところもありつつ、やっぱり人と人との関係をちょっと温かくしてくれる要素もたくさんあるんだなと実感しました。皆さんもアメリカや海外に行くとき、チップ文化を面倒に思いつつも、相手からチップを渡されたり、逆にこちらからチップを渡してみたりすることで、「ありがとう」の気持ちを分かりやすく共有してみるのもいいかもしれません。日本との違いを体験してみると、意外と面白い発見があるかもしれませんよ!